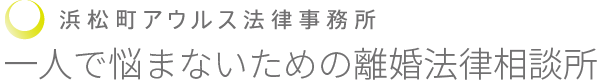裁判による離婚
目次
1. 裁判による離婚とは
裁判による離婚には、和解離婚と裁判離婚の二つがございます。
離婚を求める者が離婚訴訟を提起し、裁判手続きを進める中で、離婚について和解(合意)が成立すれば判決を待たずに和解離婚が成立し、やはり合意は難しいということであれば、判決による裁判離婚を目指すという流れが通常です。
いずれにせよ、裁判手続きですので、原則として弁護士に依頼をして、訴訟活動は弁護士に任せることをお勧めします。
2. 調停前置主義
日本のシステムでは、最初から離婚訴訟を提起することはできません。
離婚訴訟を提起する前に、家庭裁判所に対して調停を申し立て、離婚調停を経なければならないという原則がとられているためです。これを「調停前置主義」と言います。
基本的には、離婚調停において、話し合いをしたが、合意にいたらず不成立となった場合にのみ離婚訴訟の提起が認められるとお考え下さい。
3. 離婚成立までの流れ
裁判による離婚成立までの流れの概略は以下のとおりです。
-
離婚原因の存否確認
離婚訴訟においては、「離婚原因」が認められない限り離婚請求は認容されません。そのため、離婚訴訟提起前に、離婚原因が存在するか否かの確認が必須となります。
離婚原因は、民法770条1項各号で、以下の事由が定められています。ア. 配偶者に不貞な行為があったとき(同項1号)
イ. 配偶者から悪意で遺棄されたとき(同項2号)
ウ. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(同項3号)
エ. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(同項4号)。
オ. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(同項5号)-
配偶者に不貞な行為があったとき
「不貞な行為」とは、配偶者以外の者と性交渉を行うことをいいます(性交渉より広く捉える考えもあります)。
性交渉の事実は、配偶者が認める念書や、探偵業者の調査報告書、LINE等のメールのやり取りといった証拠を基に認定されます。
逆に不貞行為を行った配偶者は、有責配偶者となり、一定の要件を満たさない限り、離婚請求が認められなくなります。 -
配偶者から悪意で遺棄されたとき
いわゆる「悪意の遺棄」とは、正当な理由のないまま、配偶者に対する同居・協力・扶助義務を放棄することです。
ここで「悪意」とは、社会的・倫理的に非難されることを意味します。子どもや他方の配偶者を放置して家を出ていき、生活費の負担もしないようなケースが考えられます。 -
配偶者が3年以上生死不明
「3年以上の生死不明」とは、生存・死亡が不明である場合を言います。単なる行方不明とは異なり、生存の証明や死亡の証明もできない場合です。 -
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
配偶者が強度の精神病に罹患し、回復の見込みがない場合は、夫婦の精神的結合が失われて婚姻が破綻したと判断され、離婚原因となります。
もっとも、精神病に罹患することつき、罹患した配偶者に責任はない上、離婚が認められると他方配偶者からの援助が得られなくなるため、この事由に対する裁判所の判断は、他の事由よりも厳格だとされています。 -
婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、婚姻生活が破綻し、修復することが著しく困難な状態にあることをいいます。
夫婦の双方が、結婚生活を続ける意思がない場合や、長期に渡って別居し、交流もないような場合などです。
また、DVやモラハラ、勤労意欲の欠如、浪費・ギャンブルなども、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当することがあります。
離婚を希望される方の多くが感じておられる相手配偶者との性格の不一致は、ただちに離婚原因にはなりませんが、他の事情と相まって、離婚原因となることはあります。
-
-
離婚訴訟提起
原則として、離婚をしたいと考えている夫婦の一方が原告となり、他方配偶者を被告として、原告または被告の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、訴状を提出することで離婚訴訟を提起する必要があります。
-
管轄する裁判所とは?
離婚訴訟は、原則として、原告又は被告の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てればよいとお考え下さい。この点、相手側(被告)の住所地を管轄する裁判所に対してしか申し立てられない離婚調停とは異なっています。
例えば、夫が離婚訴訟を提起したいと考えたとき、夫は東京都港区に住んでいるが、妻は別居して茨城県内に住んでいると想定します。この場合でも、夫は、自分自身の住所地である東京都港区を管轄する東京家庭裁判所に対して訴訟提起することができるということになります。
「東京都内の管轄区域表」
(https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/tokyo/index.html) -
訴状の作成
訴状を作成し、裁判所に提出します(民事訴訟法1項)。当該訴状には以下のような事項を記載する必要があります。- 当事者及び法定代理人(民事訴訟法133条2項1号)
- 請求の趣旨及び原因(民事訴訟法133条2項2号)
- 請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない(民事訴訟法規則53条1項)。
上記(イ)(ウ)については、上記いずれの離婚原因かを明確にしつつ、重要なポイントを整理して簡潔に記載することが求められます。
そのため、お客様自身で適切な訴状を作成することは大変難しいです。
-
-
期日の指定
-
第1回口頭弁論期日
事件の配点を受けた裁判官は訴状を審査し、形式的に不備がなければ、口頭弁論期日を指定して当事者を呼び出します。
第1回口頭弁論期日においては、裁判官の指揮の下に、公開の法廷で手続が行われます。原告またはその訴訟代理人が出頭した上、事前に裁判所に提出した訴状を陳述します。被告については第1回口頭弁論期日については、事前に答弁書を提出しておけば、欠席をしても陳述したものとみなされる、擬制陳述の制度がありますので、実務上は、第1回口頭弁論期日は、被告側は欠席の場合が多いです。
離婚訴訟においては、原告も被告も、代理人をつけている場合には、基本的に代理人のみの出頭で足りますので、ご本人が裁判所に行く必要はありません。 -
2回目以降の期日
2回目以降の期日は、通常、1か月から1か月半に一度程度のペースで指定されます。2回目以降も同様に代理人がついている場合は、代理人のみの出頭で足りますのでご本人が裁判所に行く必要はありません。
-
-
訴訟活動(主張・立証)
離婚訴訟における訴訟活動は、基本的に、期日前までに準備書面と証拠を準備して裁判所に提出し、期日当日は、裁判官からその内容を確認されたり、争点を整理したりという流れになります。
そのため、事前にしっかりと自らの主張を整理して書面にまとめ、主張を裏付ける証拠を準備することが大変重要になります。 -
裁判手続きの終了
-
和解
-
離婚の成立
離婚訴訟において、訴訟上の和解により離婚を成立させることもできます(人事訴訟法37条)。簡単に申し上げますと、訴訟手続きの中で、双方が話し合いにより離婚することに合意した場合には、判決を待たずに訴訟手続きを終了させ、離婚を成立させる手続きになります。
離婚訴訟においては、一度は、裁判所から和解による離婚の検討を打診され、和解による離婚成立を検討し、それが困難となった場合に判決に向けて手続きを進めるという流れになることが多いです。 -
和解離婚成立
和解による離婚を成立させることが可能となった場合には、裁判所書記官が和解調書を作成します。
書記官が和解調書を作成した時点で、離婚が成立します。
ただし、身分関係に変動は生じるため、報告のために、和解成立後から10日以内に、離婚届の提出を行う必要があります。この場合、離婚届に相手方の署名捺印は必要ありません。
-
-
判決
-
判決
和解による離婚の成立が困難となった場合には、最終的に裁判所が双方の主張立証を踏まえて、判決を出します。
裁判所が離婚請求相当と判断すれば離婚を認める認容判決が出て、離婚が認められ、離婚請求不相当と判断すれば離婚請求は認めない棄却判決が出ることになります。 -
裁判離婚成立
離婚認容の判決が出て、判決書が送達された日から2週間以内に双方とも控訴しなければ判決が確定し、同時に離婚も成立することになります。
ただし、身分関係に変動は生じるため、報告のために、判決確定後から10日以内に、離婚届の提出を行う必要があります。この場合、離婚届に相手方の署名捺印は必要ありません。
-
-
-
不服申し立て
裁判所が判決を出したとしても、さらに上位の裁判所に対して判決内容について不服を申し立てることができます。この不服申立制度が、一般的に控訴や上告と言われるものです。
不服申し立てがなされると、判決は確定しません。
4. 和解離婚・裁判離婚成立の効果
離婚認容判決が確定した場合に、確定判決の効力が発生することはもちろんのこと、和解による離婚において和解調書が作成された場合にも、確定判決と同一の効力が発生することになります。
定められた事項について、履行されない事態となった場合に強制執行などの法的手続きがとれるというのが重要な効果です。
5. 裁判(和解)離婚という手段のメリット・デメリット
-
メリット
-
裁判所に出頭することなく手続きを進められる
代理人がついている場合、調停とは異なり、基本的に出頭するのは代理人のみでよく、当事者尋問を除いて本人が裁判所に出頭する必要がありません。そのため、相手方と直接接触する必要がないことはもちろんのこと、裁判所に行く労力もかけずに、手続きを進めることができることになります。 -
相手方の合意がない場合でも離婚が成立しうる
協議や調停という手段と異なり、裁判離婚の場合、最終的に相手方が離婚について承諾していない場合でも裁判所が相当と認めれば、離婚認容判決が出て、離婚を成立させることができます。 -
確定判決と同一の効力が得られる
確定した判決はもちろん、和解調書も確定判決と同一の効力があるため、強制執行という法的手続きがとれます。
-
-
デメリット
-
時間がかかる
期日は1ヶ月から1ヶ月半に1回程度しか入りません。加えて、訴訟にまでなるケースは財産関係が複雑であったり、争点が多数あることも多いため、主張立証にも時間を要する場合が多いです。
そのため、和解成立にしても、判決を得る場合であっても、結論が出るまでに通常1年程度、長いケースですと2年以上かかることもあります。 -
相手方(被告)に不満が残るケースが多い
裁判離婚の場合、被告が離婚を拒否していても、第1審の裁判所が離婚相当と判断すれば離婚を認容する判決が出ます。そのため、被告の不満が残ったまま結論が出ることも多く、被告からさらに上位の裁判所に対する不服申し立てがなされることも珍しくありません。
このように控訴などの不服申し立てがなされますと判決は確定せず、離婚は成立しません。この意味でも裁判による離婚は結論が出るまで長期化する傾向にあるといえます。
ただし、途中で和解離婚が成立した場合は、不服申し立ての心配はありません。そのため、和解離婚は早期解決を目指すという観点からも検討の意味がるといえます。
-
6. 弁護士への相談・依頼
日本の場合、訴訟についてもご本人で対応することは可能です。ただし、上記のように、訴状作成段階から法的知識が必須であり、判決を見据えて戦略を立てることが必要となります。
そのため、訴訟については基本的に弁護士への依頼をお勧めいたします。
訴訟については、本人で対応しようとすると、裁判所からも訴訟手続きを弁護士に依頼することを勧められることが多く、実際に、ご本人で対応されるケースは珍しいです。